『抽象化』といえば、内容が曖昧で何を言ってるか分からない。
そう思われがちですが、本当にそうでしょうか?
仕事の指示を具体的にすると上記のようなものすごく面倒な指示出しになります。
これは仕事に限らず、あらゆるコミュニケーションの場でも同様に言えるでしょう。
コミュニケーションが苦手な人は往々にして具体と抽象の使い分けが下手です。
具体とは何のか?
抽象とは何なのか?
細谷 功氏が書かれた『具体⇄抽象』トレーニングを基に解説していきます!
・指示出し、指示受けが苦手
・コミュニケーションに自信がない
抽象化
抽象化とは『まとめて1つにすること』
無数にある具体を、特定のカテゴリに分類すること
イメージとしては以下の通りです。
つまり抽象化とはあらゆる具体的な事象に対して、自由に線引きできることです。
そして必要な能力としては俯瞰した目線と自由度の高さへの柔軟性です。
冒頭の会議室の片付けを見てみましょう。
一言で『片付け』と抽象化できますが、いざ実行するとどうでしょう?
本・ファイル・文房具・食器以外にも、 椅子・机・プロジェクター・空調など片付けようとしたらキリがありません。
会議室全体を俯瞰して具体的にどこを片付けるべきかを確認する。
次の会議の予定があれば、あえて片付けない柔軟性を取り入れる。
視野の広さと臨機応変な対応こそが抽象化の根幹と言えるでしょう。
具体化
具体化とは『引かれた線の中を詳細化すること』
カテゴリ化された分類を、数値や固有名詞で表現すること
イメージとしては以下の通りです。
つまり具体化とは『青か白か』『円か三角形か』のように違いを明確化することです。
そして必要な能力としては5W1Hと共通認識です。
今度はよくあるダイエットの目標を例に考えましょう。

1.規則正しい生活を心掛ける
2.食生活を最適化する
3.余計なものを食べない
「規則正しい生活」とは何でしょうか?
「最適化」とは何でしょう?
「余計なもの」とは何でしょう?
いつ何を食べるのでしょう?
何を継続して何を辞めるのでしょう?
不明点を挙げだしたらキリがありません。
行動方針を5W1Hで表現する。
その内容が誰が読んでも共通した認識を持てる。
『痩せる』という目標は抽象的でも良いですが、そのための行動方針(KPI)は具体的でなければ、絶対に目標達成できません。
なぜなら自分でも、どう行動すれば良いのか分からないからです。
参考書籍紹介
フェルミ推定に学ぶ、地頭力向上を目的とした書籍です。
地頭力とは?フェルミ推定とは?
その2つの関係性とは?
仮説思考・フレームワーク思考・抽象化思考の3つから地頭力を底上げします。
まとめ
無数にある具体を、特定のカテゴリに分類すること
必要な能力:俯瞰した目線、自由度の高さへの柔軟性
カテゴリ化された分類を、数値や固有名詞で表現すること
必要な能力:5W1H、共通認識
いかがだったでしょうか。
『抽象化は曖昧なもの』から『抽象化は物事を一般化してまとめるもの』という認識を持てただけでも十分です。
頭が良い人や生産性がある人は、具体と抽象の往復を無意識にできます。
思考力に自信がない人は、まず意識的に相手の話している事を要約してみましょう。
また朝、夜、仕事のルーティンを5W1Hと共通認識で説明してみましょう。
これだけであなたの思考力は激変します。




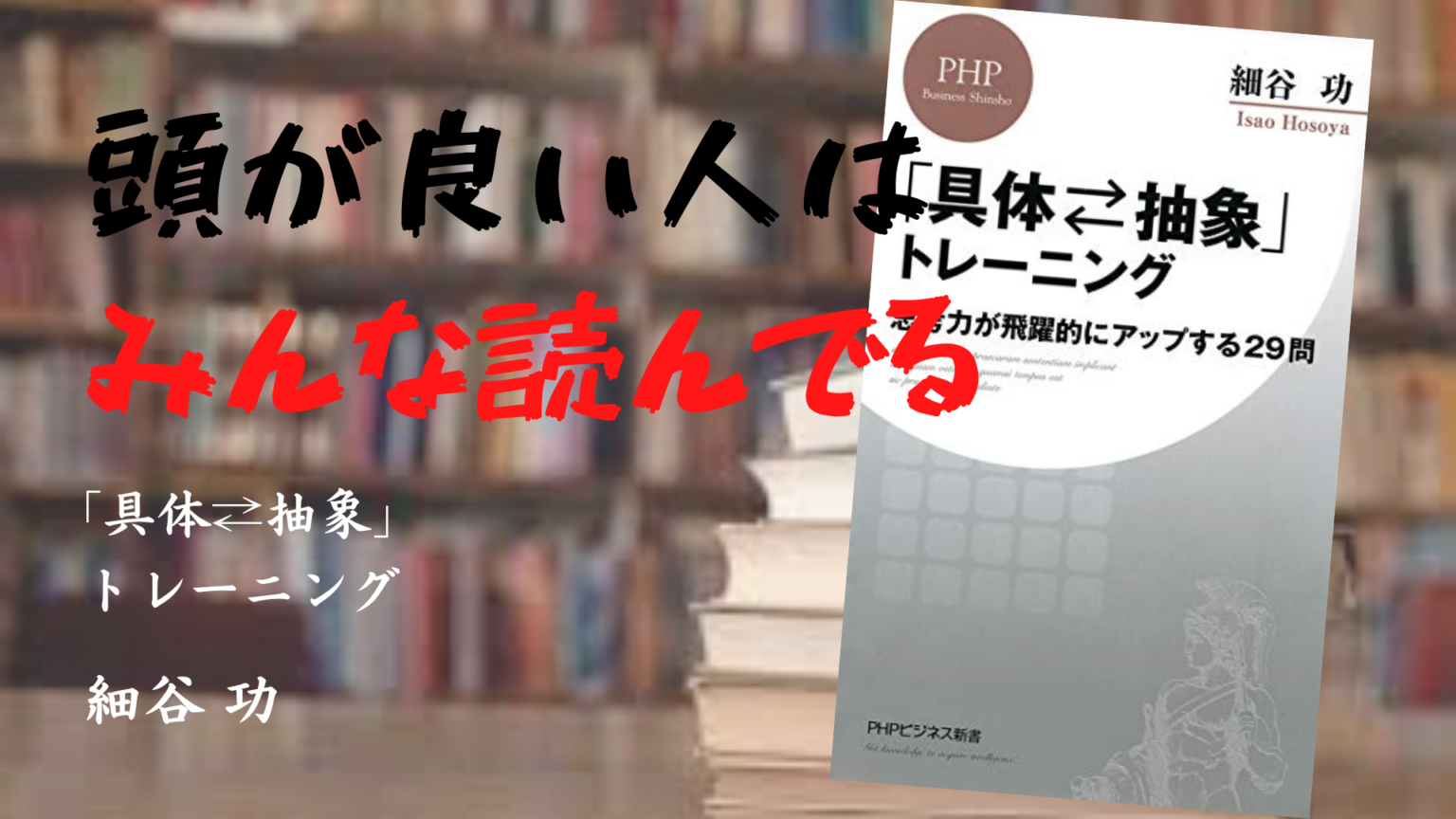


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26646cc4.aea0560b.26646cc5.1b161bb6/?me_id=1213310&item_id=19885357&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5999%2F9784569845999.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26646cc4.aea0560b.26646cc5.1b161bb6/?me_id=1213310&item_id=12635780&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5989%2F9784492555989.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


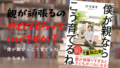
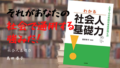
コメント